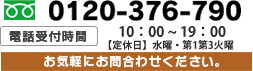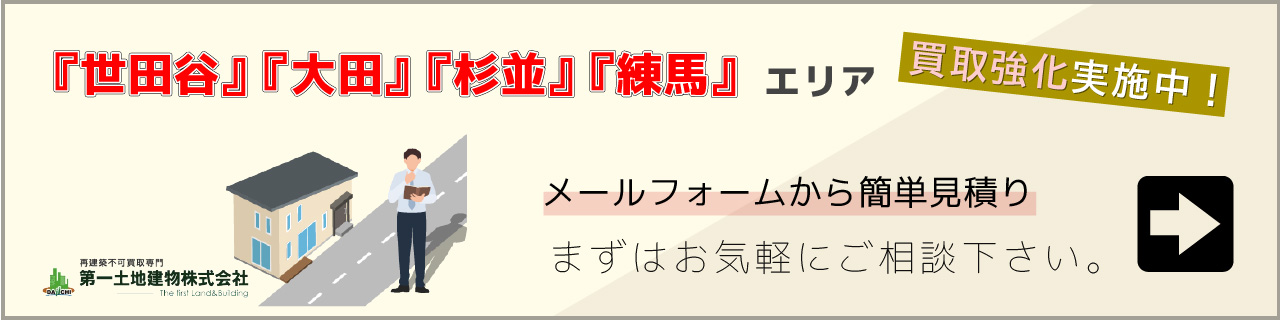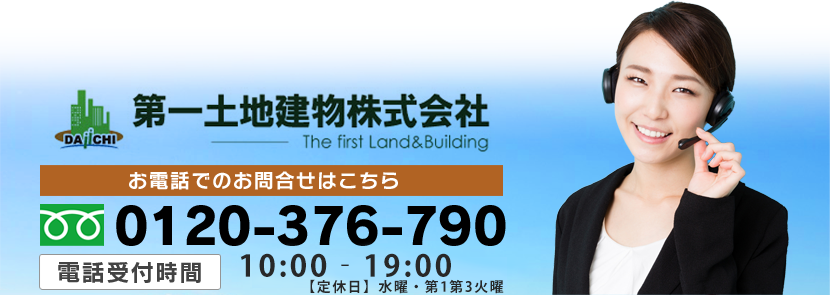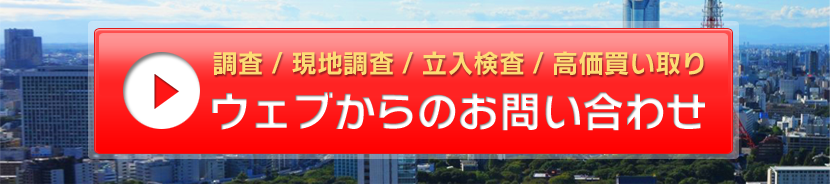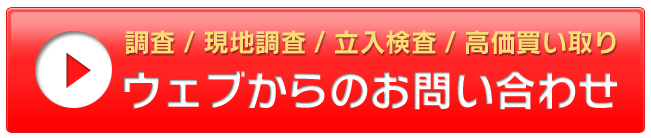再建築不可物件はどうするべき?放置するデメリットと活用方法、売却の注意点を徹底解説!
記事公開日
最終更新日 2025年2月7日

再建築不可物件の所有者となったものの、「物件をうまく活用できない」「相場がわからず売却できない」などの理由から放置してしまっている例は少なくありません。再建築不可物件を放置すると、さまざまなリスクをともないます。そのため、何らかの方法で現金化したり有効活用したりする方法を考えたいところです。
この記事では、再建築不可物件を放置することで起こる問題と、問題を回避するために考えられる物件の活用方法、売却時の注意点について紹介します。
目次
再建築不可物件をどうする?再建築できない理由
そもそも再建築不可物件は、なぜ建て直しができないのかについて解説します。
再建築不可物件とは
再建築不可物件とは、今建っている建物を取り壊して更地にしてしまうと、新たに建物を建てられない土地のことをいいます。該当するのは、都市計画区域および準都市計画区域内に限られます。
なお、建物の建て直しが認められない理由はいくつかありますが、住宅で問題になるのはおおむね以下の3つです。
1.接道義務を果たしていない
再建築不可物件で最も多いのが、接道義務違反の土地です。建物の敷地は、幅員4m以上の道路に対して、原則として間口が2m以上接道していなければならないというルールがあります(建築基準法42条、同43条)。専門用語ではこれを接道義務と呼び、接道義務に違反している場合には、建築確認が必要となる新築や増築について建築許可が下りません。
2.既存不適格物件である
建築した当時は建築基準法などの法令に適していたものの、建築基準法改正などによって現行の規定に適合しなくなった物件があります。これを既存不適格物件といいます。既存不適格物件は違法ではありませんが、現行の規定に合わせる必要があるため、現在と同一の建物に建て直すことはできません。
3.市街化調整区域内に建っている
市街化調整区域とは、無秩序な市街化を抑制する区域のことです。市街化調整区域に位置している土地で家の建て直しなどをする際は、都市計画法に基づき自治体に対して開発許可の申請が必要です。必ず許可されるとは限らないため、この場合も再建築不可とされる場合があります。
再建築不可物件をどうする?物件を放置するデメリット
再建築不可物件は、活用方法が難しい側面があることから、取得したあとも放置されがちです。しかし、再建築不可物件を放置すると、以下のような問題が発生する場合があるため、注意が必要です。
倒壊する可能性がある
建物が老朽化している場合、放置すると倒壊するリスクがあります。再建築不可物件は、建築から数十年以上経過しているものもあり、現行の耐震基準に適合していないものも少なくありません。そのため、大きな地震が発生すれば倒壊する恐れがあります。
万が一、倒壊してしまうと、同じ土地に新しい建物は建てられないため、建物を失うことになります。
特定空家等に指定されることも
建物が古く、そのまま放置すれば倒壊などのリスクがある空家は、空家等 対策特別措置法の特定空家等に認定される場合があります。特定空家等に認定されると、自治体から必要な措置を取るよう助言、指導を受けたり、改善するよう勧告の対象となったりします。
また、特定空家等が建っている土地は、固定資産税・都市計画税が減額される住宅用地としての特例措置を受けられないため、特定空家等に認定されると、固定資産税額が3倍から6倍、都市計画税が1.5倍から3倍に跳ね上がります。
近隣に損害を与える可能性がある
建物が倒壊して通行人や近隣に損害を与える可能性もあります。民事訴訟に発展し、建物の適切な管理を怠っていたことが原因であると認定された場合、損害賠償が命じられることも考えられるでしょう。
被害者が大けがをしたときや、隣家の一部を破壊してしまった場合などは、賠償額が大きくなることもあるため、早めの対策が必要です。
犯罪などに利用される恐れも
空家物件が放置されたままだと、粗大ゴミや不要品を不法に投棄される恐れがあります。不法投棄されたゴミは自分で処分しなければならず、費用も発生するでしょう。
また、第三者に不法侵入される可能性もあり、近隣住民の不安を招くほか、火災発生などのリスクも生じます。
再建築不可物件を再建築可能物件にするには?

再建築不可物件の放置はリスクが高いため、相続で取得したり知らずに購入したりしたときには、何らかの方法で物件を活用しながら適切に管理することが必要です。例えば、接道義務違反が理由で再建築不可物件となっている場合、以下の対策により再建築可能物件にできる場合があります。
セットバックする
セットバックとは、物件が面している道路が幅員4m未満である場合、道路に面した部分の敷地を後退させ、その部分を公道として提供することで接道義務を満たす方法です。道路の中心線から2mまでが道路の一部となって道路が広がります。
セットバックによって接道義務を満たせば、敷地に再建築できるようになりますが、セットバックして後退した部分の私的利用はできなくなります。建物は建てられず、庭としての活用もできなくなるなど、実質的に敷地が狭くなるため注意が必要です。
隣地を買い取って接道義務を満たす
隣地の一部またはすべてと合わせることで接道義務を満たせるのであれば、隣地を買い取って1つの土地にしてしまう方法もあります。土地を買い取るための資金と、隣人との交渉が必要ですが、物件の価値を高めて売却したい場合はおすすめです。
位置指定道路にする
自分の土地の一部を、位置指定道路にする方法もあります。位置指定道路とは、特定行政庁 から指定を受けている私道で、建築基準法上の道路として認められています(建築基準法第42条) 。最低条件は幅員4m以上か、車両の通り抜けが可能であることです。
自治体に申請し許可を受ける必要がありますが、諸条件は自治体やお住まいの地域によって異なるため、担当部署に事前に相談するとよいでしょう。
建築基準法第43条のただし書き道路許可を取得
建築基準法第43条のただし書き道路とは、特定行政庁が建築審査会の同意を得て建築を認めた道路 を指します。「周囲に広い空き地がある」「農道などに接している」「避難時に安全に利用できる通路に接している」などの条件に該当することが必要です。
許可が下りるかは、地域の状況や自治体の建築審査会の考え方によります。そのため申請は慎重に行なう必要があり、建築会社など専門家に相談するのがおすすめです。
再建築不可物件を有効活用!
上記の方法では、再建築可能物件にできない場合もあります。その場合に土地を有効活用する方法を紹介しましょう。
更地にして駐車場・駐輪場の経営
土地を更地にして駐車場や駐輪場を経営する方法です。更地にすれば建物の管理は必要なく、賃貸経営などで必要になる修繕費用も発生しません。間口が狭い土地でも敷地が広ければ、バイクや自転車の駐輪場に適しています。
この方法は、管理の手間やコストが少なく済みますが、一方で、家が建っているときと比べて固定資産税や都市計画税が高くなります。住宅地であれば、固定資産税の評価額が3分の1から6分の1、都市計画税の評価額が3分の2から3分の1になるという特例を受けられますが、更地は軽減措置の恩恵を受けられないためです。特例が適用されない点を考慮したうえで、選択肢の一つに入れるようにしましょう。
更地にしてトランクルーム経営
更地にする場合、コンテナを設置してトランクルーム(貸倉庫)の経営を行なうことも可能です。立地などの条件が良ければ、実質的な利回りが20%、高ければ30%に達することもあります。
建築基準法に基づく確認申請(建築基準法第6条) が必要となるほか、一度更地にする手間と費用はかかるものの、初期費用はコンテナの購入費のみで、ランニングコストもかからないため、軌道に乗ればコストパフォーマンスの高い投資といえます。
更地にして家庭菜園として利用
農業やガーデニングを楽しみたい方は、更地にして家庭菜園を作ってもよいでしょう。自分で使うだけでなく、近所の方に貸し出すことも可能です。
十分な広さがあるのであれば、本格的に貸農園を経営し、賃料や利用料で収益を得ることも考えられます 。貸農園は、土地に手を加える必要がほぼないため、ほかの土地活用に比べて初期費用をかけずに始められる点もメリットです。
リフォームをして賃貸経営
再建築不可物件の場合、新しい建物を建てられない代わりに、既存の建物のリフォームは可能です。リフォームすれば快適に住み続けられるほか、フルリフォームで新築同様にできれば、高めの家賃を設定しても借り手が見つかる可能性は高くなります。あるいは古民家カフェなどに改築し、店舗テナントにしてもよい でしょう。
なお、再建築不可物件は建物が老朽化していることが多く、リフォーム費用が高額になりやすい点に注意が必要です。投資した費用をどのくらいの期間で回収できるか、需要のある立地かどうかなども見極めたうえで、リフォームするかどうか判断することになります。また、以下のような決まりがある点にも留意しましょう。
リフォームができるのは建築確認申請が不要な範囲のみ
再建築不可物件はこれまで、建築確認申請が不要な範囲であれば工事が可能とされてきました。
建築確認申請は、建築基準法第6条で定められており 、原則として、「新築」「増築」「改築」「移転」「用途変更」「大規模の修繕」「大規模の模様替え」の際に行なわなければならない申請 のことです。
一方で、建築確認申請が不要な工事もあります。例えば「防火地域・準防火地域を除く、床面積10㎡以下の増築・改築・移転」や「4号建築物の大規模な修繕・模様替え」などです 。
なお、「4号建築物」とは以下 を指します。
・学校や病院など、建築基準法における「特殊建築物」以外である
・木造の場合は、2階建て以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下
・木造以外の場合は、1階建て以下、延べ面積200㎡以下
また、「大規模な修繕・模様替え」とは、建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の1種類以上について行なう、2分の1を超える 修繕もしくは模様替えを指します 。
上記のことから、これまでは再建築不可物件でも4号建築物であれば建築確認申請が不要であり、大規模なリフォームも可能と解釈されてきました。
しかし、2025年の建築基準法改正により、再建築不可ではない通常の建物で大規模修繕・模様替えを行なう場合、建築確認申請が必要になります 。そのため、再建築不可物件も同様に、大規模なリフォームはできなくなると考えられるでしょう。
参考:国土交通省「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」
再建築不可物件でのリフォーム例
再建築不可物件でよくあるリフォーム例は、以下のとおりです。
・耐震補強や耐火性の向上
・断熱性の向上
・キッチンやトイレ、浴室など水回りの交換
・壁や床など内装材の張り替えや、窓の交換
耐震や耐火、断熱性の向上に関するリフォームが行なわれると、安全面や快適性が増し、売却もしやすくなるでしょう。ただし、大規模な工事になる可能性も高くなり、リフォームの範囲によっては、新築購入と同じくらいの費用がかかることもあります 。
再建築不可物件をどうする?売却も検討しよう!

ここまで再建築不可物件を有効利用し、放置リスクを抑えつつ収益を生み出す方法を紹介してきました。しかし、いずれの方法も多少なりとも費用負担が発生するため、実行が難しいと感じた方もいるでしょう。
そのような場合は、売却も選択肢の一つになります。以下に、売却を検討する際に注意したいポイントを紹介します。
更地にするのは活用方法が決まってから
建物を壊して更地にするのは、土地の活用方法が決まってから行なうのがおすすめです。再建築不可物件は、更地にしてしまうと建物の新築ができず、売却がより難しくなる可能性があるためです。
また、更地にすると「住宅用地の特例」の対象外となり、固定資産税や都市計画税が大幅に増額します。そのため、建物がどれほど古くてもすぐには壊さず、更地にする前に活用方法をしっかり検討することが大切です。
すでに更地の場合は活用の検討を
相続した場合などで、すでに更地になっている土地については、接道義務をクリアすることで再建築可能物件にならないかを確認しましょう。
あるいは、駐車場やトランクルームなどに活用できないかを検討し、固定資産税など税金分だけでも収益を得られるようにするのがおすすめです。
売却を検討する場合は隣人への相談も選択肢の一つ
土地活用が難しい場合は、売却を検討することになります。ただし、再建築不可物件は、土地利用に制約があることや住宅ローン審査が通りにくいことなどから、売却のハードルは高いといえます。
そこで一つの選択肢として、隣人が売却を検討していないか、相談してみる方法があります。隣地と合わせることで間口の狭さや接道義務をクリアできれば、売却できる可能性も高まるでしょう。反対に、同じ理由で隣人が買取を検討している可能性もあります。
ただし、隣人との交渉は、金額面などでトラブルになるリスクも否めません。相手と日頃からコミュニケーションが取れている場合や、転居するタイミングなどに相談するのがおすすめです。あるいは、隣地の所有者が亡くなった場合は、相続した親族が土地の扱いに困っている可能性もあるため、様子をうかがってみてもよいでしょう。
不動産会社に相談する
売却する際には、専門の不動産会社に相談することをおすすめします。
売却には「仲介」と「買取」の2つがあり、仲介よりも買取のほうが売却の可能性が高まります。一方で、仲介に比べて買取は売値が落ちる傾向にあります。特に、再建築不可物件の買取は、土地の再活用など投資目的の場合が多く、一般の居住目的による購入よりも金額は低くなりがちです。
一般的な不動産会社では、再建築不可物件の買取ができない場合や、価値を正しく評価できない場合があります。
そこで、不動産会社を選ぶ際には、再建築不可物件の買取実績があるかを事前に確認するとよいでしょう。再建築不可物件に特化した不動産会社であれば、物件の調査から査定、買取まで一貫して 行なってもらえるほか、古家付きの土 地や残置物のある物件 もそのまま買い取ってくれる場合があります。
不動産会社の買取実績はWebサイトで公開されていることが多いため、候補の不動産会社のWebサイトをチェックしたうえで問い合わせるのがおすすめです。
■まとめ
再建築不可物件は、放置したままにしておくと状態が悪化して倒壊したり、特定空家等として認定されたりする懸念がでてきます。このような事態を避けるためには、再建築可能物件にするか、リフォームをするなどして資産価値を高める方法があります。あるいは、収益物件として土地の再活用を考えていくのがよいでしょう。
初期費用が捻出できず収益化が難しいといった場合は、売却を検討する必要があります。ただし、再建築不可物件は、土地利用に制約があることから売却のハードルも高いため、専門の不動産会社に相談するのがおすすめです。
第一土地建物株式会社は、再建築不可物件など訳あり物件の買取を専門に行なっており、他社から買取不可といわれた物件も積極的に査定しています。建物の状態が悪い、土地の境界が確定していないなど、難のある物件も大歓迎です。ぜひお気軽にご相談ください。
年間100件以上を扱う第一土地建物なら、お客様のご要望に応じた買取プランをご用意いたします。
お問い合わせから引渡しまでの流れ
-
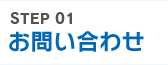
- お電話または問合わせフォームよりお問合わせください。

-
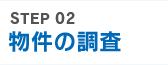
- 再建築可能か不可か調査し、再建築不可であれば、可能に出来るのかも含めて調査致します。

-

- 再建築が可能な場合と再建築不可だった場合での査定額を迅速に提示致します。

-

- 物件の査定額にご納得いただければご契約の流れになります。

-

- 最終残代金をお支払いした後、鍵のお引き渡しになります。
再建築不可買取の関連コラム一覧
お知らせ・ニュース
- 2025年12月23日
- 冬季休業のお知らせ
- 2023年12月24日
- 冬季休業のお知らせ
- 2023年8月1日
- 夏季休業のお知らせ
- 2023年4月21日
- ゴールデンウィーク休業のお知らせ
- 2022年12月13日
- 冬季休業のお知らせ
- 2022年4月18日
- 2022年GW休業のお知らせ
- 2021年4月12日
- 2021年GW休業のお知らせ
- 2021年1月9日
- 新年のご挨拶
- 2020年12月7日
- 冬季休業のお知らせ
- 2020年8月1日
- 夏季休業のお知らせ