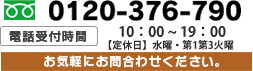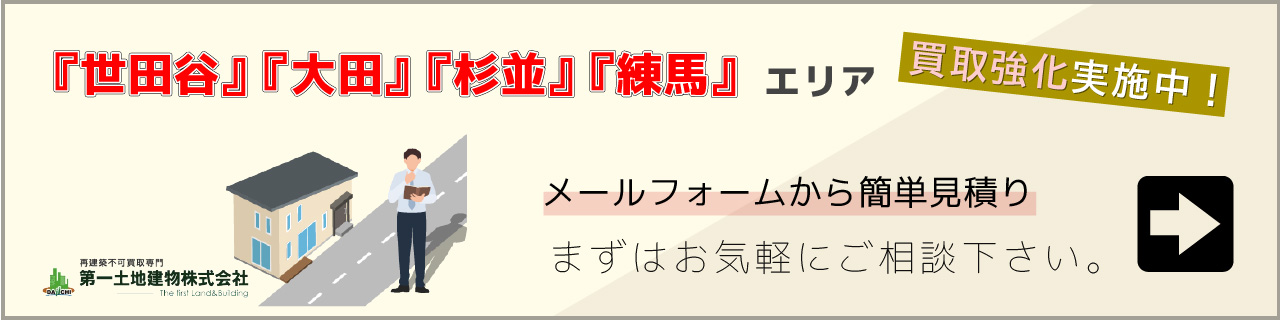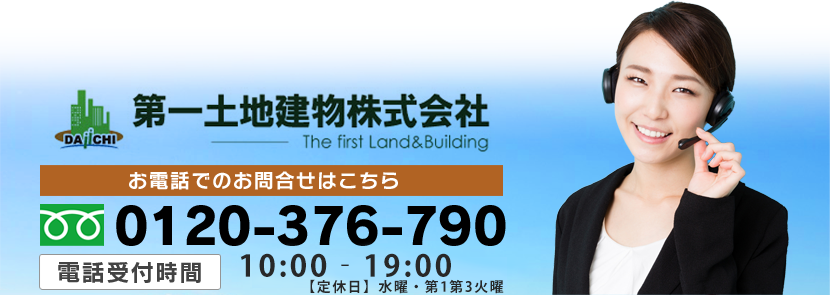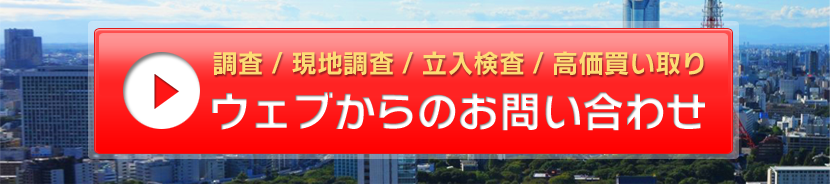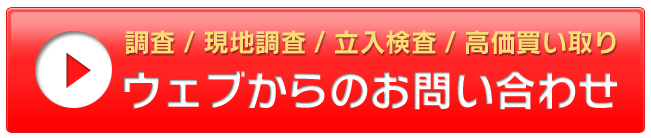再建築不可にも影響する2025年建築基準法改正!おもな変更点と今後を解説
記事公開日
最終更新日 2024年9月12日

2025年4月に予定される建築基準法改正では、建築確認申請における特例が縮小され、再建築不可物件のリフォームにも影響が出ると考えられます。再建築不可物件を所有している方のなかには、法改正に対して漠然とした不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、法改正の内容と変更のポイントを解説。再建築不可物件で今後出てくると思われる、法改正による影響や対策について紹介します。
目次
2025年4月法改正で「4号特例」縮小へ
2025年4月に予定される建築基準法改正で「4号特例」が縮小されることとなっており、木造の建物を中心に影響が出る見込みです。「4号特例」がどのように変わるのか、そもそも建築確認申請とは何なのか見ていきましょう。
建築基準法の「4号特例」とは?
「4号特例」とは、建築基準法第6条で規定される「4号建築物」において、建築士が設計した、または建築士が設計どおりの施工が実施されたことを確認した際には、建築確認申請が不要となる特例のことを指します。
なお、都市計画区域などに該当する地域においては建築確認申請が必要です。改正前である現行法で4号建築物に該当する建築物は、次の要件に当てはまる建築物が該当します。
- ● 木造2階建て以下で延べ面積500平方メートル以下のもので、かつ下記に該当しないもの
- ・高さ13メートル超え、軒高9メートルを超えるのもの
- ・店舗や車庫、共同住宅などの特殊建築物の場合は200平方メートルを超えるもの
- ● 木造以外の平屋建て、かつ延べ面積200平方メートル以下のもの
改正後は、上記の4号建築物が「新2号建築物」「新3号建築物」へ見直されます。これにより、地域を問わず建築確認審査が必要となる建物の範囲が広がる予定です。
法改正が行なわれる背景には、建築物省エネ法の改正にともなう省エネ対策の強化や、性能強化による重量化がもたらす倒壊リスクの回避が求められていることなどがあります。
建築基準法に沿っていることを確認する「建築確認申請」
建築確認申請とは、新築、大規模改修・増改築を行なう際、着工前に実施する申請のことをいいます。設計内容を確認検査機関や特定行政庁へ申請して確認を受け、建築基準法をはじめとする法令に適合している旨を証明するための手続きです。
建築確認申請が必要なケースでは、申請が通らないと法的に適合した設計・構造であることが認められないため、建築することができません。
関連記事:確認申請をしないと建築基準法違反?申請が必要な理由と工事までの流れ
2025年4月法改正での変更ポイント
2025年4月の建築基準法改正による4号特例の縮小では、特に押さえておくべきポイントがあります。再建築不可物件にも影響する可能性のある大きな2つの変更点を紹介します。
建築確認申請が必要な対象が拡大
1つ目のポイントは、大規模なリフォームを行なうとき、建築確認申請をしなければならない建物が増えることです。改正後は「新2号建築物」「新3号建築物」が新設されます。
4号建築物のうち、木造2階建てと延べ面積200平方メートルを超える木造平屋は「新2号建築物」に該当し、審査省略制度(4号特例)の対象外となります。つまり、これらの建物で大規模な修繕・模様替えを実施する場合、建築確認申請が求められるようになるのです
「新3号建築物」では従来どおり建築確認申請が不要ですが、該当するのは延べ面積が200平方メートル以内に収まる木造平屋のみです。リノベーションなどで申請対象となるケースが大幅に増えると考えられます。
建築確認申請時の必要書類が増加
4号特例では、建築確認時に準備しなければならない必要書類が一部省略されています。しかし、2025年4月以降の新2号建築物では、構造や省エネに関する図書が申請時の必要書類に追加され、今までよりも多くの書類を準備する必要が生じます。
なお、新3号建築物に関しては現行と同様、必要書類の提出が一部省略されます。
再建築不可物件が今後リフォームしづらくなる理由

4号特例が縮小されると、内容によっては再建築不可物件をリフォームするのが今後しづらくなる可能性があります。
これは、再建築不可物件は現行法の基準を満たさない「既存不適格」の状態にあるため、建築確認申請で建築許可が下りないことが関係しています。現行でも、再建築不可物件における建築確認申請を要するリフォームや模様替えは原則不可。4号建築物に該当する場合のみ、大規模修繕や模様替えも実施可能です。
「大規模な修繕・模様替え」とは、建築物の主要構造部の1種類以上について半分超を修繕・模様替えすることを指します。また、主要構造部とは壁、柱、床、梁、屋根、階段などのことです。
法改正後、再建築不可物件の場合、建築確認申請が不要な延べ面積200平方メートル以下の木造平屋しか大規模な修繕・模様替えができなくなります。そのため、再建築不可物件の多くで大規模なリフォームができなくなると考えられるのです。
今後も再建築不可物件で可能なリフォーム
反対に法改正後も、再建築不可物件で実施できるのはどのようなリフォームなのでしょうか。内容を確認していきましょう。
建築確認申請が不要な小規模なリフォームや模様替え
再建築不可物件で実施できるか否かの境界線は「建築確認申請が必要かどうか」というところにあります。建築確認申請が不要な小規模リフォームや模様替えであれば、法改正後も変わらず実施できる一方、旧4号建築物における大規模な修繕・模様替えは実施できなくなるでしょう。
建築確認申請がいらない小規模リフォームの事例としては、主要構造部に手を加えない内装だけのリフォームなどが挙げられます。ちなみに「最下階の床」は主要構造部から除外されるため、1階部分の床をやり変えるのは大規模な修繕・模様替えに該当せず、再建築不可物件でも実施が可能です。
床面積200平方メートル以下の木造平屋の大規模リフォーム
法改正後「新3号建築物」に分類される床面積が200平方メートル以内の木造平屋であれば、主要構造部の半分以上に手を加える大規模なリフォーム・模様替えであっても、建築確認申請は従来どおり不要です。再建築不可物件だったとしてもそれは同様になります。
加えて、防火地域または準防火地域の外にある建物では、10平方メートル以下の増改築も建築確認申請が不要なため、再建築不可物件でも実施できます。
ハードルが高い再建築不可物件の建て替えや大規模リフォーム
法改正によって、大規模リフォームが難しくなることが想定される再建築不可物件。建て替えや大規模リフォームを実現するには、再建築不可になっている要因を排除して、再建築可能な状態にする必要があります。
要因として多いのが「接道義務違反」です。建築基準法において、建物の敷地は原則、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが求められています。これを「接道義務」といい、満たさない敷地には原則建物を建てることができません。接道義務違反を解消して再建築可能にするには、次のような方法が有効です。
- ● 隣接地を購入、借りるなどして接道を2メートル以上確保する
- ● 前面道路が4メートルに満たないときはセットバック(土地を後退)して道幅を確保する
- ● 建築基準法第43条のただし書きの適用を申請する
再建築可能にする方法はこちらの記事で詳しく解説しています。
再建築不可物件を再建築可能にする抜け道・裏ワザとは?
ただ、いずれの方法も個人の希望がそのまま通るとは考えにくく、実現のハードルは高いでしょう。
法改正前の今のうちに第一土地建物へ売却のご相談を!
ここまで紹介してきたように、2025年4月の法改正によって、再建築不可物件の大規模なリフォームは難しくなると考えられます。法改正後は物件のニーズが下がり、活用や売却の難易度が上がる可能性も否定できません。
接道義務違反を解消するなど、建て替えや大規模リフォームを可能にする方法もありますが、いずれもハードルが高くなっています。そこでおすすめなのが専門の会社に買い取ってもらう方法です。
再建築不可の専門家である第一土地建物なら、スピーディかつ高値での買い取りを実現できます。これまでも数多く再建築不可物件を買い取りした実績があるので安心です。法改正によりリフォームが難しくなる前に、ぜひ第一土地建物へお気軽にご相談ください。
再建築不可物件の実績|第一土地建物
第一土地建物について詳しくはこちら
まとめ
2025年4月の建築基準法改正で「4号特例」が縮小され、大規模リフォーム時に建築確認申請をしなければならない建物が大幅に増える見込みです。再建築不可物件も多くが申請対象となるため、法改正以降は大規模リフォームの実施が難しくなるかもしれません。
接道義務違反をクリアする方法はいずれもハードルが高いので、所有する再建築不可物件の活用にお悩みの方は、専門会社による買い取りを早めに検討するのがいいでしょう。
年間100件以上を扱う第一土地建物なら、お客様のご要望に応じた買取プランをご用意いたします。
お問い合わせから引渡しまでの流れ
-
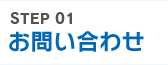
- お電話または問合わせフォームよりお問合わせください。

-
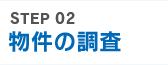
- 再建築可能か不可か調査し、再建築不可であれば、可能に出来るのかも含めて調査致します。

-

- 再建築が可能な場合と再建築不可だった場合での査定額を迅速に提示致します。

-

- 物件の査定額にご納得いただければご契約の流れになります。

-

- 最終残代金をお支払いした後、鍵のお引き渡しになります。
再建築不可買取の関連コラム一覧
お知らせ・ニュース
- 2023年12月24日
- 冬季休業のお知らせ
- 2023年8月1日
- 夏季休業のお知らせ
- 2023年4月21日
- ゴールデンウィーク休業のお知らせ
- 2022年12月13日
- 冬季休業のお知らせ
- 2022年4月18日
- 2022年GW休業のお知らせ
- 2021年4月12日
- 2021年GW休業のお知らせ
- 2021年1月9日
- 新年のご挨拶
- 2020年12月7日
- 冬季休業のお知らせ
- 2020年8月1日
- 夏季休業のお知らせ
- 2020年7月28日
- 新規物件を買取致しました!