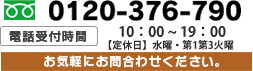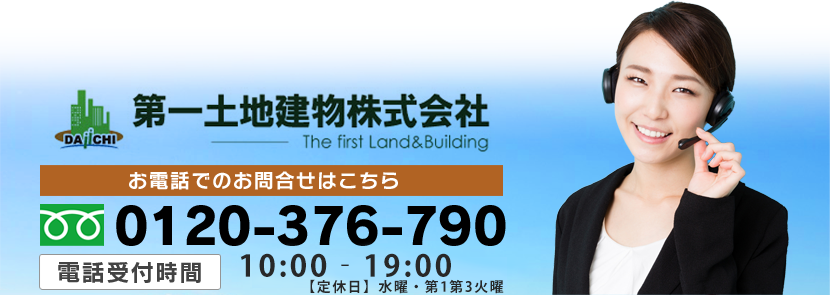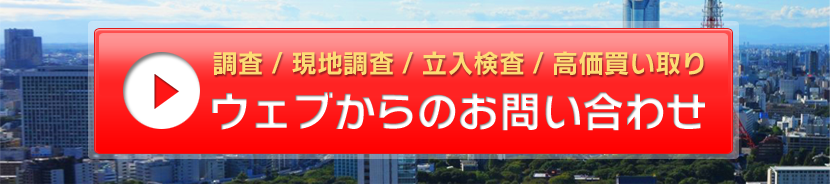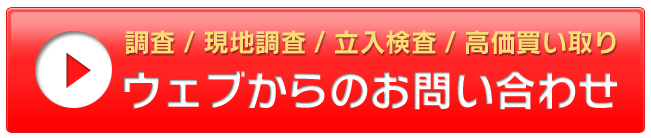建築基準法における耐震基準とは?新旧の違いや耐震補強についても解説
記事公開日
最終更新日 2024年3月18日

地震大国と呼ばれる日本で建築物を建てる際には、建築基準法で定められた耐震基準を満たす必要があります。耐震基準は建築基準法の改正にともない変化するため、現行の基準を理解したうえで、耐震補強などの対策を講じることが大切です。
この記事では、耐震基準の概要や変遷、新耐震基準を満たすメリット、耐震補強などについて解説します。新旧の耐震基準の違いについて知りたい方、ご自宅の耐震補強工事を検討している方などは、ぜひ参考にしてください。
目次
■建築基準法における耐震基準とは?
「耐震基準」とは、地震が発生しても倒壊・損壊しない建築物を建てることを目的に、建築基準法で定めている「最低限満たすべき」基準です。新たに建てる建築物は、耐震基準に基づいた設計や建築をする必要があります。
現行の耐震基準をクリアしている建築物は、震度6強~震度7 程度の強い地震が発生しても、倒壊・崩壊といった大きなダメージを受けにくいとされています。
そもそも耐震とは?
「耐震」とは、地震の揺れに耐えるという意味です。建築物の耐震強度を高めるために、壁に筋交いを入れたり、金具で補強したりするなどの方法が採用されています。地震が多い日本の建築物では、このような耐震工法が多く採用されています。
耐震工法を採用するメリットは以下のとおりです。
強い揺れでも建築物の倒壊を免れる
導入コストが比較的抑えられるため取り入れやすい
台風対策としても有効
一方で耐震工法のデメリットとして、以下が挙げられます。
揺れ自体は伝わりやすいため、家具が転倒するなど 建築物内へのダメージがある
倒壊は免れても建築物へのダメージは抑えられない
メンテナンス費用がかかる
制震・免震との違い
地震に対する工法には、耐震工法のほかにも制震工法・免震工法と呼ばれるものがあります。それぞれの意味や特徴について解説します。
・制震
「制震」とは、建築物に伝わった揺れを吸収して、揺れ自体を抑えるという意味です。制震工法では、ダンパーや重しを制震材として建築物の内部に組み入れます。
倒壊の危険性が少なく、余震にも強いというメリットがある一方で、導入できる地盤が限られている、耐震工法よりも導入コストが高いなどのデメリットがあります。
・免震
「免震」とは、地震の揺れを建築物に直接伝えずに、受け流すことです。建築物と地盤との間に、揺れを吸収するゴムやダンパーなどの免震装置を組み込む工法がとられています。
免震工法を導入すると大きな地震でも揺れにくく、建築物を守るだけでなく、家具の転倒なども抑えられる点がメリットです。デメリットとしては、3つの工法のなかで最も導入コストが高い、比較的新しい工法のため施工可能な業者が限定される、などが考えられます。
■建築基準法改正にともなう耐震基準の変遷

ここでは、新旧耐震基準の違いや、繰り返されている法改正の歴史について解説します。
新耐震基準と旧耐震基準の違い
新耐震基準と旧耐震基準の大きな違いは、おもに大規模地震についての基準です。
・新耐震基準
新耐震基準とは、1981年6月1日 に導入された基準です。最大震度5を記録した宮城県沖地震(1978年6月12日発生) において、多数の被害があったことをきっかけ改正されました。
新耐震基準では「中規模地震(震度5強)でほぼ損傷せず 、大規模地震(震度6強~7程度)でも倒壊・崩壊しない」ことが求められています。
・旧耐震基準
旧耐震基準は、新耐震基準が導入されるまでの1981年5月31日以前に、建築確認が行なわれた建築物に適用されている基準です。新耐震基準と区別するためにこのように呼ばれています。
旧耐震基準は「中規模地震(震度5強)で倒壊しない」という程度にとどまっており、大規模地震については想定されていません。そのため、旧耐震基準で建設された建築物は、今後大規模地震が起こった際に大きな被害を受けるおそれがあります。
建築基準法改正の歴史
耐震基準を定めている建築基準法は、これまで何度も改正を繰り返しています。その歴史と時代背景を時系列で紹介します。
1920年:建築関連の法律として「市街地建築物法 」が施行される。構造強度に対する規則も含まれており、建築基準法の原型となる。
1924年:市街地建築物法施行規則 が改正される。1923年の関東大震災を経て、初めて耐震基準が導入される。
1950年:市街地建築物法が廃止 され、建築基準法が施行される。このとき、旧耐震基準も規定される。
1971年:1968年に発生した北海道十勝沖地震の影響を受け、建築基準法の改正が行なわれる。RC造の建築物の耐震基準が引き上げられる。
1981年:1978年に発生した宮城県沖地震の影響を受け、建築基準法が改正される。それにともない、震度7程度までを想定した新耐震基準が規定される。
2000年:1995年の阪神淡路大震災を経て、建築基準法が改正され、木造住宅の耐震基準が引き上げられる。同年には通称「住宅品質確保促進法」 も施行され、耐震等級や住宅性能表示について規定された。
■【建築基準法】新耐震基準を満たすメリット

旧耐震基準で建てられたまま、現在も使われている建築物は少なくありません。建て替えやリフォームによって新耐震基準を満たすことで、得られるメリットについて解説します。
地震対策になる
まず挙げられるメリットは、建築物の耐震性が上がることです。大型の地震が発生した際の建築物が倒壊するリスクが減り、安全性が高まります。
資産価値が高まる
旧耐震基準で建てられたままの建築物よりも、新耐震基準を満たしている建築物のほうが資産的価値は高く評価されます。いずれ売却を予定している建築物であれば特に、新耐震基準を満たしておいたほうがよいでしょう。
税制上の優遇措置を受けられる
新耐震基準を満たすことで受けられる、税制上の優遇措置は少なくありません。代表的なものとして、住宅ローン減税、不動産取得税や固定資産税の軽減などが挙げられます。なお、軽減の度合いや条件などは自治体によって異なります。
フラット35が使える
旧耐震基準で建てられた建築物であっても、リフォームなどにより新耐震基準に適合していることを証明できれば、長期固定型住宅ローンである「フラット35」を活用できます。「フラット35」は保証人が不要で、繰上返済手数料も不要な制度です。
補助金を受けられる
新耐震基準を含む一定の条件を満たすことで、さまざまな補助金を受けられる可能性があります。代表的なものは、国土交通省による「長期優良住宅化リフォーム推進事業 」です。
この他にも、自治体が独自で用意している制度もあるため、着工前に探してみましょう。
■【建築基準法】再建築不可物件でも耐震補強はできる?
再建築不可物件に該当する建築物は、原則としては改築や増築が認められていません。そのため、一度取り壊して新耐震基準に沿った建築物を新築するのは不可能です。
しかし、自治体への建築確認申請が不要な範囲であれば、耐震補強工事をともなうリフォームが行なえます。
通常、大規模なリフォーム(フルリフォーム)を行なう場合は建築確認申請が必要ですが、下記に該当する物件なら、フルリフォームでも建築確認申請が免除されます。再建築不可物件であっても旧耐震基準から新耐震基準へとランクアップさせることが可能です。
木造住宅の場合:2階建て以下/延べ床面積500平方メートル以下
鉄骨造住宅の場合:1階建て/延べ床面積200平方メートル以下
ただし、耐震補強込みでリフォームを行なう場合、新築物件の購入と変わらないほどの高額な費用がかかるケースも珍しくありません。また、建築物を取り巻く環境によっては耐震補強工事ができない可能性もあるため、それぞれの状況に応じて対応する必要があります。
■まとめ
地震が多い日本で建築物の安全性を確保するには、建築基準法によって定められている耐震基準を満たすことが大切です。
旧耐震基準で建てられたままの建築物は、リフォームなどで新耐震基準に適応する方法を検討する価値があるでしょう。原則、増改築が認められていない再建築不可物件は、一定の条件を満たすことで耐震補強をともなうフルリフォームが可能です。
第一土地建物では、再建築不可物件の買い取りを積極的に行なっています。売却先が見つからずお困りのケースでも、ぜひご相談ください。
年間100件以上を扱う第一土地建物なら、お客様のご要望に応じた買取プランをご用意いたします。
お問い合わせから引渡しまでの流れ
-
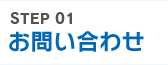
- お電話または問合わせフォームよりお問合わせください。

-
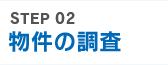
- 再建築可能か不可か調査し、再建築不可であれば、可能に出来るのかも含めて調査致します。

-

- 再建築が可能な場合と再建築不可だった場合での査定額を迅速に提示致します。

-

- 物件の査定額にご納得いただければご契約の流れになります。

-

- 最終残代金をお支払いした後、鍵のお引き渡しになります。
再建築不可買取の関連コラム一覧
お知らせ・ニュース
- 2023年12月24日
- 冬季休業のお知らせ
- 2023年8月1日
- 夏季休業のお知らせ
- 2023年4月21日
- ゴールデンウィーク休業のお知らせ
- 2022年12月13日
- 冬季休業のお知らせ
- 2022年4月18日
- 2022年GW休業のお知らせ
- 2021年4月12日
- 2021年GW休業のお知らせ
- 2021年1月9日
- 新年のご挨拶
- 2020年12月7日
- 冬季休業のお知らせ
- 2020年8月1日
- 夏季休業のお知らせ
- 2020年7月28日
- 新規物件を買取致しました!